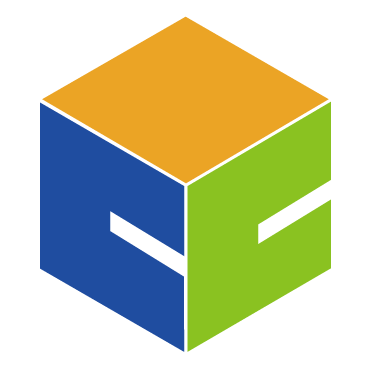物流業界の2025年問題とは?
法律改正から対策まで徹底分析!

物流業界は今、かつてない変革の波に直面しています。2024年4月からのドライバーの時間外労働規制強化に続き、2025年4月には物流効率化法と貨物自動車運送事業法が改正・施行されました。これらの法改正は、単に運送事業者だけでなく、荷主企業を含むサプライチェーン全体に大きな影響を与えています。
この記事では、物流業界の2025年問題の本質を解き明かし、改正された2つの法律の詳細、業界の現状、そして直面している7つの主要課題について解説。さらに企業が今すぐ取り組むべき対策方法や、実際に物流DXに成功した事例もご紹介します。
人手不足、DXの遅れ、積載効率の低下、長い待機時間、再配達問題、薄利多売の構造、環境配慮への対応。これらの複合的な課題に対し、どのように向き合えば良いのか。本記事を最後までお読みいただければ、 2025年問題の全体像を理解し、自社が取るべきアクションが明確になるはずです。
物流業界の2025年問題とは?

物流業界の「2024年問題」の影響は2025年以降も続き、むしろ本格化するという見方があります。
そもそも、物流業界における2025年問題とは、労働力人口の減少と時間外労働の上限規制による諸問題を指します。 2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に年間960時間という上限が設けられ、長時間労働が不可能となりました。 1日あたりに運べる荷物の量が自然と減少し、業界全体で輸送できる荷物量の減少は避けられない状況となりつつあるのです。
さらに深刻なのは、物流業界におけるデジタル化の遅れです。他業界と比べてDXが進んでおらず、 従来のアナログな業務プロセスが効率化の妨げとなっています。配達状況の確認に電話を使い、 配送依頼書の送付にFAXを用いるなど、旧来の方法に依存している企業も少なくありません。
▶「2024年問題」について詳しくはこちら:ドライバー不足で荷物が運べなくなる? 運送会社にできる2024年問題対策とは
2025年4月から改正・施行された2つの法律を解説!

このような複合的な問題に対処するため、政府は2025年4月に「物流効率化法」と「貨物自動車運送事業法」を改正・施行しました。 物流の効率化、商慣行の見直し、荷主および消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策を講じることを目的としています。
これは物流業界にとって極めて重要な転換点となる法改正と言っても過言ではありません。 物流効率化法と貨物自動車運送事業法の主な内容について解説しましょう。
01物流効率化法
物流効率化法は、正式名称を「物資の流通の効率化に関する法律」といい、従来の「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から名称が改められました。 この法律の最大の特徴は、荷主・物流事業者・連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部など)のすべてに物流効率化のための努力義務を課している点です。
具体的には、2028年度までに2つの重要な数値目標が設定されています。 第一に、5割の運行で1運行あたりの荷待ち・荷役時間を計2時間以内に削減すること。第二に、5割の車両で積載効率50%を実現することです。
荷主に求められる主な取り組みには以下があります。
●パレット等の活用による荷役時間の削減
●予約受付システムの導入による荷待ち時間の短縮
●発注・納品の平準化
●配送頻度の見直し
物流事業者には、輸配送の共同化・モーダルシフトの推進、自動化・機械化による作業効率の向上、配送ルートの最適化などが求められます。
さらに重要なのは、一定規模以上の事業者が「特定事業者」として指定され、より厳格な義務を負うということです。 特定事業者には、物流統括管理者の選任、物流効率化に向けた中長期計画の策定と提出、定期的な実施状況の報告が義務付けられます。
国は、各事業者の取り組み状況を判断基準に基づいて評価し、必要に応じて指導・助言を行っています。 優良事例や不十分な事例について調査・公表を行うことで、業界全体の取り組みを促進していく方針なのです。
▶「物流効率化法」について詳しくはこちら: 物流総合効率化法とは?2024年の法改正や支援措置・物流業界への影響も解説
02貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法は、1989年に施行された法律で、トラック運送業に関するルールを定め、 輸送の安全性の向上と事業の健全な発達を図ることを目的としています。 2025年4月の改正では、取引環境の適正化と安全対策の強化という2つの柱が設けられました。
第一の柱である取引環境の適正化では、運送契約締結時の書面交付が義務化されました。 荷主・トラック事業者・利用運送事業者は、運送契約を締結する際に、 提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)を記載した書面を交付しなければなりません。
第二の柱である安全対策の強化では、特に軽トラック事業者に対する規制が新設されました。 近年、軽トラック運送業において死亡・重傷事故件数が急激に増加しており、安全対策の強化が大きな課題となっていました。 改正法では、軽トラック事業者に対し、貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講が義務付けられます。
これらの規制により、物流業界の取引環境は大きく変わることとなります。特に書面交付義務は、荷主企業にとっても重要な変更点です。 今のところ違反に対する罰則は設けられていませんが、貨物自動車運送事業者については行政処分の対象となる可能性があり、荷主についても是正指導の対象となる場合があります。
2025年の物流業界の状況とは?

ここまでお話ししてきた通り、2025年の物流業界は、目まぐるしい変化が起きています。 法改正の施行、市場構造の変化、消費者行動の多様化など、様々な要因が複雑に絡み合いながら、業界全体に影響を与えているのです。
ここでは、市場規模、消費者動向、経営状況という3つの視点から、現在の物流業界を取り巻く状況を詳しく見ていきましょう。
01市場規模
物流業界の総市場規模は、約32兆円と推計されています。この数字は物流が日本経済において極めて重要な位置を占めていることを示しており、 内訳を見るとトラック運送業が約16兆円と全体の約6割を占めていて、国内貨物輸送の9割以上がトラック輸送に依存している実態が浮き彫りになります。
市場規模の推移を見ると、2023年度から2025年度にかけて、物流市場規模は横ばいもしくは微増の傾向にあります。 調査によると、2024年度の物流15業種総市場規模は24兆6,405億円、2025年度は24兆7,650億円と予測されており、前年度比でわずか0.5%の成長に留まる見込みです。
この背景には、半導体不足の解消により自動車輸送などが好調に推移する一方、米国関税の引き上げの影響による輸出貨物量の低迷、 国内ではコロナ禍から徐々に回復しているものの、物価上昇による消費活動の低迷の影響で取扱物量は横ばいのままといった原因が見られています。
しかし、物量が横ばいであっても、運賃や料金などの価格上昇により市場規模は拡大しているという点を見逃してはいけません。 これは、人件費の上昇や燃料費の高騰、環境対応のための投資コストが、荷主への価格転嫁という形で表れていることを意味します。
02消費者の動向
消費者の行動変化は、物流業界に直接的かつ大きな影響を与えています。最も顕著なのは、EC市場の拡大による宅配便需要の急増です。 2020年度には約48億個、2021年度には約50億個と、宅配便の取扱個数は堅調に増加を続けています。これは過去30年で約4倍という驚異的な伸び率です。
EC市場の成長を支えているのは、スマートフォンやタブレットの普及により、いつでもどこでも簡単にネットショッピングができるようになったという環境の変化です。 特にコロナ禍を契機に、オンラインでの購買行動が加速しました。
しかし、この需要増加は物流業界にとって両刃の剣となっています。消費者ニーズの多様化により、当日配送や翌日配送といった迅速なサービスへの期待が高まり、 配送のスピードと正確性がこれまで以上に求められるようになりました。 さらに、小口多頻度配送の増加は、トラックの積載効率を低下させ、配送コストの増加につながっています。
2023年、政府が「送料無料」の表示見直しに取り組む方針を打ち出したことで、商品には必ず運送コストが含まれているという認識が広がりつつあり、物流に関わるすべての人々が、持続可能な物流システムを構築するために協力し合う必要性が、社会全体で共有されるようになってきています。
03経営状況
物流業界の経営状況は、厳しい局面を迎えつつあり、 市場規模が拡大しているにもかかわらず、多くの事業者が収益性の低下に苦しんでいるのが実情です。その最大の要因は、コスト上昇圧力と価格転嫁の困難さにあります。
物流事業者が直面するコスト増加要因は多岐にわたり、人件費や燃料コスト等の上昇が挙げられます。 2024年4月からの時間外労働規制の強化により、ドライバーの労働時間が制限され、同じ業務量をこなすためには人員増が必要となりました。
さらに深刻なのは、近年の運送業者の倒産件数の増加です。2023年の道路貨物運送業の倒産は328件を記録し、前年と比べて32.2%も増加しました。 人手不足、燃料費高騰、労働時間規制という複合的な課題に対し、経営努力だけでは対応しきれなくなっている事業者が増えていることを示しています。
このような厳しい経営環境の中で、業界ではM&A(企業の合併・買収)が増加しています。 大企業はM&Aを通じてドライバーを確保したり、事業規模を拡大して新たな市場に進出したりといった対策が顕著です。
2025年問題が浮上した背景にある課題7つを解説!

2025年問題は、単一の原因によって引き起こされたものではありません。 長年にわたって物流業界に蓄積されてきた構造的な課題が、時間外労働規制という法改正をきっかけに一気に顕在化したものです。
ここでは、2025年問題の背景にある7つの主要課題について詳しく解説します。
01DXの遅れ
物流業界におけるDXの遅れは、2025年問題を深刻化させる最大の要因の一つです。 他の業界と比較して、物流業界ではデジタル技術の導入や活用が大幅に遅れており、未だにアナログで労働集約型の作業スタイルから脱却できていない現場が少なくありません。
具体的には、配達状況の確認に電話を使い、配送依頼書の送付にFAXを用いるといった業務プロセスが今でも一般的です。 物流センターでは、トラックが到着してから荷降ろしする荷物の内容を知り、そこから保管先を検討するという非効率な運用が行われているケースもあります。 このような状況では、配車の最適化やリアルタイムでの在庫管理、需要予測といった高度な物流管理は到底実現できません。
DXが進まない背景には、いくつかの理由がありますが、中小企業を中心にシステム投資に充てる資金的余裕がないという問題が大きいです。 物流業界の99%を占める中小企業にとって、数百万円から数千万円に及ぶシステム導入費用は大きな負担であるのが実態です。
しかし、DXは物流業界の生産性向上と競争力維持のために避けては通れない道です。 自動運転トラックの導入、ドローンによる配送、AIを活用した需要予測や最適配送ルートの算出、倉庫の自動化など、先進技術を活用する機会は豊富にあります。
02人手不足
物流業界における人手不足は年々深刻さを増していて、特にトラックドライバーの不足は危機的状況にあり、 2027年には日本のトラックドライバーが24万人不足すると予測されています。 それは業界全体の輸送能力に直接的な影響を及ぼし、2030年には約3割の荷物が運べなくなる可能性も指摘されているのです。
人手不足の根本的な原因は、日本全体の少子高齢化と人口減少です。労働人口全体が減少する中で、物流業界はとりわけ人材確保に苦戦しています。 トラックドライバーの多くが40代以上であり、60代も増加傾向にあります。若年層の新規参入が少ないため、業界全体の高齢化が急速に進んでいるのです。
若者が物流業界、特にトラックドライバーという職業を敬遠する理由はいくつかあります。 最も大きいのは労働環境の厳しさです。長時間労働が常態化しており、厚生労働省の調査によると、 トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均より約2割も長くなっています。
加えて、2024年4月からの時間外労働規制により、ドライバーの収入減少という新たな問題も浮上しています。 労働時間が制限されることで、これまで残業代で収入を補っていたドライバーの手取りが減少し、結果として離職が増えるという悪循環が懸念されています。
03積載効率
トラックの積載効率の低下も、物流業界が抱える深刻な課題の一つです。 積載効率とは、トラックの最大積載量に対して実際にどれだけの荷物を積んでいるかを示す指標ですが、近年この数値が年々低下しているのが実情です。
積載効率が低下している主な原因は、EC市場の拡大による小口多頻度配送の増加です。消費者ニーズの多様化により、 当日配送や翌日配送といった迅速なサービスへの期待が高まり、十分な積載量を確保できないまま配送するケースが増えています。 大手ECサイトでは、1回の注文に対して複数回の配送が行われることもあり、これが積載効率を大きく押し下げる要因となっているのです。
積載効率の低下は、様々な問題を引き起こします。たとえば、運行回数が増えることでドライバーの労働負担が増加。 燃料費などの輸送コストが増大し、収益性が悪化したり、トラックの運行回数が増えた分だけCO2排出量も増加し、環境負荷が高まってしまいます。
この課題に対する解決策として、AIによる配送計画の最適化、企業間での共同配送、貨物のシェアリングサービスの活用などが進められています。改正物流効率化法でも、 2028年度までに5割の車両で積載効率50%を実現することが目標として掲げられており、今後も業界全体で積載効率の向上に取り組む機運が高まっていくでしょう。
04長い待機時間
トラックドライバーの長い待機時間(荷待ち時間)は、物流業界の生産性を大きく損なう要因となっています。 国土交通省の2024年の調査によると、1運行あたり平均1時間28分の荷待ち時間が発生しており、これがドライバーの長時間労働の主要な原因の一つとなっています。
荷待ち時間とは、荷物の積み下ろしのためにトラックドライバーが待機している時間のことです。 具体的には、物流施設に到着したものの、他のトラックが列をなして待機しているときに順番を待つ時間、 荷主側の荷物の準備が完了していないために積み込みができずに待機する時間、指定時間に合わせるための時間調整などが含まれます。
荷待ち時間が発生する主な原因は、
●倉庫の出荷体制が整っていないこと
●受付や指定時間が集中する時間帯であること
●トラックバース(荷物の積み降ろしを行う場所)の不足
●天候や交通状況による車両到着時間のずれ
などです。これらの問題が複合的に作用し、長時間の荷待ち時間を引き起こしています。
この課題に対し、政府は「荷待ち・荷役作業等時間2時間以内ルール」を示しました。 荷主事業者が物流事業者に対して荷待ちや荷役作業にかかる時間を原則として計2時間以内に収めることを求める規定です。 標準貨物自動車運送約款の改正により、待機時間料が新たに規定され、運送会社が荷主に対して有責待機の対価を請求しやすくなりました。
05再配達
再配達問題は、消費者の行動が直接的に物流の効率性に影響を与える典型的な課題です。国土交通省の2024年10月の調査では、 宅配便の再配達率は約10.2%を記録しています。2023年10月の約11.1%からは改善しているものの、 依然として約10個に1個の荷物が再配達されている計算になります。
再配達が発生する主な原因は、受取人の不在です。配達時に在宅していなかったため、ドライバーは同じ場所に再度訪問しなければなりません。 この非効率な運行は、ドライバーの労働負担を大幅に増加させるだけでなく、CO2排出量の増加にもつながり、環境面でも大きな問題となっています。
再配達削減に向けて、様々な取り組みが進められています:
●宅配ボックスの設置による不在時の受け取り対応
●置き配サービスの活用(玄関先や指定場所への配置)
●コンビニ受取や駅の宅配ロッカーの利用
●時間帯指定の活用(ゆとりある日時の指定)
政府も再配達削減を物流効率化の施策として位置づけています。 消費者一人ひとりが、物流の現状を理解し、できる範囲で協力することが、持続可能な物流システムの構築に繋がります。 再配達削減は、消費者の行動変容が鍵を握る課題なのです。
06薄利多売
物流業界は、長年にわたって薄利多売の構造に苦しんできました。 運賃が低く抑えられる一方で、取扱量を増やすことで利益を確保するというビジネスモデルが定着しており、これが業界の収益性を大きく損なっています。
薄利多売の構造が生まれた背景には、運送業界の過当競争があります。トラック運送業の中小企業率は99%と極めて高く、 多数の事業者が限られた荷物を奪い合う状況が続いています。荷主企業との力関係において、運送事業者は立場が弱く、 運賃交渉において不利な条件を受け入れざるを得ないケースも少なくありません。
この状況を打破するため、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法では、運賃と料金を明確に区分し、書面で交付することが義務化されました。 標準的な運賃の告示では、荷役作業料の割増料金が最低でも30分で2,000円ほど、最高水準で時給換算すると5,500円にもなる設定がなされています。
薄利多売からの脱却は、物流業界の持続可能性を確保するための最重要課題の一つです。 適正な運賃・料金の収受は、ドライバーの賃金向上、労働環境の改善、そして人材確保にも直結します。 荷主企業の理解と協力のもと、公正な取引環境を構築していくことが求められています。
07環境配慮
環境配慮は、物流業界にとって避けては通れない課題となっています。日本政府は2050年までのカーボンニュートラル実現を目指しており、 物流業界にも大きな役割が期待されています。 2022年度の日本の二酸化炭素排出量10億3,700万トンのうち、運輸部門からの排出は1億9,180万トン(18.5%)を占めており、その過半数がトラック輸送によるものです。
物流業界が環境負荷削減に取り組むべき理由は、単に規制への対応だけではありません。 環境配慮は企業の社会的責任であり、ステークホルダーからの期待も高まっています。環境に配慮した物流は、長期的にはコスト削減にも繋がるのです。
環境負荷削減に向けた具体的な取り組みは多岐にわたり、例えば電動トラックやハイブリッドトラックなど、環境に優しい車両への転換が進められています。国土交通省は「物流脱炭素化促進事業」を開始し、 太陽光発電の設置や大容量蓄電池の確保、EV充電スタンドの用意などの一定の条件を満たすと、費用の2分の1まで(上限あり)の補助が出る制度を整備しました。
倉庫や物流センターにおける省エネ化も進んでおり、LED照明の導入、太陽光発電システムの設置、空調設備の効率化などにより、 エネルギー消費量を削減する取り組みが広がっています。環境配慮は、もはや付加的な取り組みではなく、物流業界の競争力を左右するともいえる経営戦略となっているのです。
物流業界で2025年問題に対策する方法とは?

2025年問題に直面している物流業界ですが、 この危機をチャンスに変える方法は確実に存在します。単なる問題対処ではなく、持続可能で競争力のある物流システムを構築するための戦略的アプローチが欠かせません。
ここでは、企業が今すぐ取り組むべき3つの対策方法について解説します。
01多様なドライバーを雇う
人手不足に対する最も直接的な解決策は、労働力の確保です。しかし、従来と同じ方法では、若い男性ドライバーを採用することは困難です。 そこで手段の一つとなるのが、多様な人材を積極的に受け入れるという発想の転換です。
まず、女性ドライバーの採用拡大が挙げられます。 現状、トラックドライバーは圧倒的に男性が多い職業ですが、女性にとっても魅力的な職場環境を整備することで、新たな人材層を開拓できます。
業界全体のイメージ改善も不可欠です。「3K」というネガティブなイメージを払拭し、 DXによる働きやすい環境、適正な賃金、キャリアパスの明確化などをアピールすることで、 者にとって魅力的な職業として認識されるよう努めていく必要があるといえるでしょう。
02デジタル化を進める
デジタル化は、2025年問題を解決するための最も強力なツールです。物流DX(デジタルトランスフォーメーション)により、業務の効率化、労働環境の改善、 コスト削減を同時に実現できます。
物流DXで導入すべき主なシステムは以下の通りです:
●輸配送管理システム(TMS):配車計画の最適化、配送ルートの自動設定、リアルタイムでの配送状況の可視化
●倉庫管理システム(WMS):入荷、保管、ピッキング、出荷といった倉庫内作業のデジタル管理
●トラック予約受付システム:事前予約によるバース混雑の回避、荷待ち時間の削減
TMSの導入により、AIを活用した最適な配送ルートの算出が可能となり、 経験の浅いドライバーでも効率的な配送が実現できます。属人的な業務からの脱却が図れ、業務の標準化が進みます。
WMSでは、バーコードやRFIDを活用した在庫管理により、リアルタイムで正確な在庫情報を把握可能です。 欠品や過剰在庫を防ぎ、倉庫内作業の効率が飛躍的に向上するほか、作業指示もシステムから自動的に出されるため、作業員の判断ミスや漏れを防ぐことができるのです。
トラック予約受付システムは、荷待ち時間削減に直接的な効果があります。事前にトラックの到着時間を予約することで、 バースの混雑を回避し、スムーズな荷積み・荷卸しが可能となります。ドライバーの待機時間が減少し、 労働時間の短縮と業務効率の向上を同時に達成できるでしょう。
03ソフト・ハードを標準化する
物流業界全体の効率化を実現するためには、標準化が不可欠です。 各企業がバラバラのシステムや規格を使用していては、企業間連携や情報共有が困難となり、業界全体の生産性向上は望めません。
まずソフトウェアの標準化としては、EDI(電子データ交換)システムの統一が挙げられます。 受発注、配送指示、請求などのデータフォーマットを標準化することで、異なる企業間でもスムーズな情報連携が可能となります。
ハードウェアの標準化では、パレットやコンテナの規格統一が要となります。現状、企業ごとに異なるサイズのパレットを使用しているため、 積み替えや保管に無駄が生じています。標準パレットの導入により、トラックへの積載効率が向上し、荷役作業も簡素化されるでしょう。
標準化の推進には、業界全体での協力が不可欠です。個別企業の利益だけでなく、業界全体の競争力向上という視点から、積極的に標準化に取り組むことが求められています。 政府も物流DXの一環として標準化を強力に推進しており、各種ガイドラインや支援策が整備されつつあります。
物流DXに成功したコモンコムの事例を紹介!

2025年問題への対策として、実際に物流DXに取り組み、成功を収めている企業の事例を確認することは、具体的な方向性を把握するうえで大切です。
実際に、物流システムの専門企業であるコモンコムが提供する運送・倉庫システム「LOGI-Cube」を導入することで、改善に向かった物流企業の事例が数多くあります。
ここでは、コモンコムがサポートを実施した企業の事例を通じて、物流DXの具体的な効果を見ていきましょう。
01各拠点でのシステムを統合

ある運送事業者では、複数の営業所がそれぞれ独自のシステムや手法で業務を行っており、全社的な情報共有や管理が困難という課題を抱えていました。 本社が各拠点の状況をリアルタイムで把握することができず、経営判断に必要なデータの収集にも時間がかかっていました。
この課題に対し、クラウド対応の「LOGI-Cube」を全拠点に導入することで、システムの統合を実現しました。クラウドシステムの最大の利点は、インターネット環境さえあれば、 どこからでも同じシステムにアクセスできることです。各拠点の業務データは自動的に本社のサーバーに集約され、リアルタイムでの情報共有が可能となりました。
システム統合により、配車状況、売上データ、車両稼働率など、経営に必要なあらゆる情報を本社で一元管理できるようになりました。スピード感のある経営判断が可能となり、 各拠点への適切な指示や支援も行えるようになっただけでなく、拠点間での協力配送や車両の融通なども容易になり、全社的な業務効率が大幅に向上しています。
システムの操作方法が全拠点で統一されたことで、従業員の異動や応援がスムーズになり、組織全体の柔軟性も高まりました。拠点ごとに異なる手法で業務を行っていた時代と比べ、 ノウハウの共有や業務改善の取り組みも格段に進めやすくなったのです。
▶本事例について詳しくはこちら:拠点ごとにシステムがバラバラ全拠点に統合システム導入にて効果絶大
02Excel管理からの脱却
別の事業者では、配車計画や売上管理をExcelで行っており、データ入力の手間や転記ミス、情報の属人化といった問題に悩まされていました。 特に繁忙期には、配車担当者が深夜まで残業してExcelシートを更新する状況が常態化しており、担当者の負担が極めて大きくなっていました。
「LOGI-Cube」導入後、配車計画から請求書発行までの一連の業務がシステム内で完結するようになりました。 配車情報を入力すれば、自動的に運行管理、売上計上、請求書作成までが連携して処理されるため、データの二重入力や転記作業が不要となり、入力ミスも激減したのです。
データがシステム上に蓄積されることで、過去の配送実績の分析や、繁忙期の予測なども可能となったこともプラスに働いています。経営層は、リアルタイムのダッシュボードで会社の状況を把握でき、 データに基づいた経営判断ができるようになりました。Excel管理からの脱却は、単なる業務効率化だけでなく、経営の質的な向上ももたらしたのです。
▶本事例について詳しくはこちら:Excel管理からのシステム化は難しい?
2025年問題が心配な方はコモンコムへ相談!

物流業界の2025年問題は、確かに深刻な課題です。しかし、適切な対策とシステム導入により、この危機をビジネスチャンスに変えることができます。 コモンコムは、物流業界に特化したシステム開発とコンサルティングを提供する専門企業として、多くの運送・倉庫事業者の課題解決を支援してきました。
株式会社コモンコムが提供する「LOGI-Cube」は、運送業務と倉庫業務の両方に対応したクラウドシステムです。 配車管理、運行管理、請求管理、在庫管理など、物流業務に必要な機能を備えており、使い勝手の良さと豊富な機能で、導入しやすく操作は簡単という評判を頂いております。
コモンコムは福岡本社をはじめ、埼玉、新潟、静岡の国内4か所に拠点を構えており、全国どこでも対応が可能です。遠隔サポート体制も整備し、物流業界のDXを強力に推進中です。
2025年問題への対応にお悩みの方・物流DXを検討されている方は、ぜひコモンコムにご相談ください。課題に合わせた最適なソリューションをご案内いたします。
詳しくはコモンコムの公式サイトまで
LOGI-Cube STORAGE(ロジキューブストレージ)