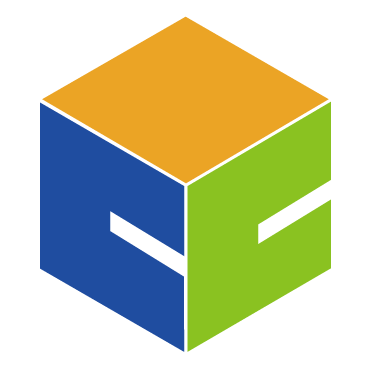物流総合効率化法とは?2024年の法改正や支援措置・物流業界への影響も解説

物流業界は近年、人手不足や環境問題といった様々な課題に直面しています。これらの課題を解決するために国が積極的に推進しているのが「物流総合効率化法」です。
この法律は物流の効率化と環境負荷の低減を同時に実現することを目指しています。本記事では物流総合効率化法の概要や2024年の法改正、 支援措置、さらには物流業界への影響について詳しく解説します。
物流総合効率化法とは?2024年の法改正も解説

物流総合効率化法について正しく理解することは、物流業界で働く方々にとって非常に重要です。この法律の基本的な内容と2024年に行われた法改正について詳しく見ていきましょう。
01物流総合効率化法とは?
物流総合効率化法は、正式名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」といい、2005年に制定されました。 この法律は物流の効率化と環境負荷の低減を同時に実現することを目的としています。 具体的には、物流施設の集約化や輸送網の共同化、モーダルシフトなどの取り組みを支援し、効率的で環境に優しい物流システムの構築を促進するものです。
物流総合効率化法では、事業者が国土交通大臣の認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。 認定を受けるためには、輸送の合理化や環境負荷の低減などの一定の基準を満たした総合効率化計画を作成し、申請する必要があります。この法律によって、 物流事業者は設備投資や運営面での支援を受けながら、効率的な物流システムを構築することが可能になります。
また、この法律は単なる効率化だけでなく、CO2排出量の削減など環境面での改善も重視しています。 トラック輸送から鉄道や船舶への転換(モーダルシフト)や共同配送の推進などにより、環境負荷の少ない物流の実現を目指しています。
02物流総合効率化法の2024年の法改正
2024年の物流総合効率化法の改正では、従来の枠組みをさらに拡充し、物流DXの推進や労働環境の改善に焦点を当てた内容が盛り込まれました。特に注目すべき点は、 デジタル技術を活用した物流効率化への支援強化です。AI・IoTなどの先端技術を活用した物流システムの導入が新たに支援対象として追加されました。
また、物流施設の省人化・自動化設備への投資支援も拡充されています。 労働力不足が深刻化する中、無人搬送車(AGV)や自動仕分けシステムなどの導入を促進することで、少ない人員でも効率的な物流を実現できるよう支援体制が整えられました。
さらに、グリーン物流への取り組み強化も今回の改正のポイントです。 環境負荷を低減する取り組みとして、電気自動車やFCV(燃料電池車)などの次世代自動車の導入支援が拡充されました。 CO2排出削減目標の達成に向けて、環境に配慮した物流への転換を加速させる内容となっています。
加えて、中小物流事業者への支援措置も強化されました。 大手物流事業者だけでなく、地域の物流を支える中小事業者も総合効率化計画の認定を受けやすくなるよう、申請手続きの簡素化や補助率の引き上げなどの措置が講じられています。
物流総合効率化の支援対象となる施策や支援措置

物流総合効率化法では、認定を受けた事業者に対してさまざまな支援が行われます。 ここでは具体的にどのような施策が支援対象となるのか、また実際にどのような支援措置が受けられるのかについて詳しく解説します。
01物流総合効率化の支援対象となる施策
物流総合効率化法では、物流の効率化と環境負荷低減を両立させる様々な取り組みが支援対象となっています。ここでは代表的な5つの施策について詳しく見ていきましょう。
●輸送網の集約
輸送網の集約は、物流効率化の基本となる重要な施策です。複数の物流事業者の輸送網を統合し、効率的な配送ルートを構築することで、 車両の走行距離削減や積載率の向上を図ります。
従来は各社が個別に配送ルートを設定していたものを、 エリアごとに最適化することで、トラックの台数削減やドライバーの労働時間短縮にもつながります。 特に過疎地域などの配送効率が悪いエリアでは、複数事業者による輸送網の集約が効果を発揮します。
●モーダルシフトの推進
モーダルシフトは、トラック輸送から環境負荷の少ない鉄道や船舶による輸送への転換を指します。 距離輸送において特に効果を発揮するこの施策は、CO2排出量の削減と輸送効率の向上を同時に実現します。
例えば、500km以上の長距離輸送を鉄道に切り替えることで、CO2排出量を約9分の1に削減できるというデータもあります。 また、ドライバー不足が深刻化する中、長距離トラック輸送の負担軽減にも寄与する重要な取り組みといえます。
●共同配送の実施
共同配送は、 複数の荷主や物流事業者が協力して配送を行う取り組みです。 特に都市部の配送において効果的なこの施策は、車両の稼働率を向上させ、物流コストの削減と環境負荷の低減を図ります。
例えば、同じエリアに配送する異なるメーカーの商品をひとつの車両にまとめることで、 配送効率が大幅に向上します。また、納品先での荷受け作業の効率化にもつながり、サプライチェーン全体の生産性向上に寄与します。
●物流施設の高度化・効率化
物流施設の高度化・効率化は、保管・荷役作業の効率向上と労働環境改善を目指す施策です。自動倉庫システムやロボット技術を活用した物流施設の整備を支援し、人手不足の解消にも貢献します。
具体的には、無人搬送車(AGV)や自動ピッキングシステムなどの導入により、作業効率を大幅に高められます。 また、IoT技術を活用した在庫管理システムの導入により、在庫の最適化や作業の可視化も進み、より効率的な物流オペレーションが実現可能となります。
●物流情報システムの構築
物流情報システムの構築は、デジタル技術を活用した効率化の要となる施策です。 荷主と物流事業者間の情報共有を円滑にするシステムの導入を支援し、配車や在庫管理の最適化を図ります。
リアルタイムの情報共有により、無駄な輸送や過剰在庫を削減できるだけでなく、急な配送計画の変更にも柔軟に対応可能となります。 また、ビッグデータやAIを活用した需要予測なども組み込むことで、より高度な物流最適化が実現できるようになります。
02物流総合効率化法の支援措置
物流総合効率化法に基づく支援措置は、資金面からの支援と規制緩和の二つに大別されます。まず資金面では、設備投資に対する税制優遇措置が挙げられます。 認定事業者は物流施設や設備の導入にあたり、特別償却や税額控除などの優遇を受けることができます。
また、各種補助金の優先採択も重要な支援措置です。物流効率化に関わる国の補助事業において、認定事業者が優先的に採択される仕組みが整えられています。 特に環境負荷低減に資する設備導入に関しては、補助率が高く設定されることが多いです。
さらに、政府系金融機関による低利融資も支援措置の一つです。 日本政策金融公庫などの政府系金融機関から、通常より低い金利で融資を受けることができ、大規模な設備投資の負担を軽減することが可能です。
規制緩和面では、都市計画法等の特例措置が設けられています。認定事業者は物流施設の建設にあたり、開発許可の特例などの規制緩和を受けることができ、スムーズな事業展開が可能となります。
また、市街化調整区域における物流施設開発の規制緩和も重要です。 通常、市街化調整区域での開発は厳しく制限されていますが、認定を受けることで、物流施設の立地が可能になる場合があります。
03物流総合効率化法の支援のための認定基準
物流総合効率化法の支援を受けるためには、事業者が作成した総合効率化計画が国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 認定を受けるためには、いくつかの重要な基準を満たす必要があります。ここでは、認定基準の主要な5つのポイントについて詳しく解説します。
●物流の効率化
認定基準の最も基本的な要素は「物流の効率化」です。提出する総合効率化計画では、輸送コストの削減や作業効率の向上など、物流業務の効率化に明確に寄与する取り組みであることを示す必要があります。
具体的には、輸送距離の短縮率や車両の積載率向上、作業時間の削減率など、定量的な指標を用いて効率化の効果を示すことが求められます。 また、効率化によってどの程度のコスト削減が見込まれるかなど、経済的な効果も明確に提示することが重要です。 計画段階では具体的な数値目標を設定し、その達成に向けた具体的な方策を示すことが認定の鍵となります。
●環境負荷の低減
二つ目の重要な基準は「環境負荷の低減」です。 物流総合効率化法の目的の一つは環境に優しい物流の実現であるため、CO2排出量の削減など、環境への負荷を低減する効果が明確に示されていることが必要です。
計画には、現状のCO2排出量と実施後の予測排出量を比較し、削減率を具体的に提示することが求められます。例えば、モーダルシフトによる排出量削減効果や、 共同配送による走行距離短縮に伴う排出削減量など、具体的な数値とその算出根拠を示すことが重要です。 目標値だけでなく、その実現可能性を裏付けるデータや実績も提示できると、より説得力のある計画となります。
●持続可能性の確保
三つ目の基準は「持続可能性の確保」です。一時的な効果を狙った取り組みではなく、長期にわたって持続可能な物流システムの構築に寄与する計画であることが重要です。
計画には、初期投資だけでなく、運用段階でのコスト構造や収益性も含めた事業計画を示し、経済的に持続可能であることを明らかにする必要があります。 また、技術面でも陳腐化しにくいシステムを採用することや、人材育成計画を含めるなど、長期的な視点での持続可能性を担保する要素を盛り込むことが評価につながります。 単なる一時的なコスト削減ではなく、将来の物流環境の変化にも対応できる柔軟性を持った計画であることを示すことが重要です。
●新規性・先進性
四つ目の基準は「新規性・先進性」です。単なる既存の取り組みの延長ではなく、新たな視点や技術を取り入れた先進的な計画であることが高く評価されます。
特に、AIやIoTなどのデジタル技術を活用した物流DXや、カーボンニュートラルに向けたグリーン物流への取り組みなど、 業界の課題解決に資する先進的な内容は重視される傾向にあります。ただし、実証されていない技術に過度に依存するのではなく、 実現可能性と革新性のバランスが取れた計画であることが求められます。他の事業者のモデルケースとなり得るような先駆的な取り組みは、認定において高い評価を受けることが多いです。
●事業者間連携
五つ目の基準は「事業者間連携」です。単独事業者による取り組みよりも、複数の事業者が連携して行う計画は優先的に認定される傾向があります。
荷主と物流事業者の連携や、複数の物流事業者による共同事業など、業界全体の効率化につながる取り組みが特に重視されています。 連携によって、個社では実現が難しい大規模な効率化や、広範囲にわたる環境負荷低減効果が期待できるためです。 計画には、各事業者の役割分担や連携のメリットを明確に示し、連携体制の安定性や継続性についても言及することが重要です。 異業種間の連携など、新たな視点を取り入れた連携の形も高く評価される傾向にあります。
物流総合効率化法施行の背景

物流総合効率化法が制定された背景には、日本の物流業界が抱える構造的な課題があります。 これらの課題は相互に関連しており、個々の事業者の努力だけでは解決が難しいものでした。 そこで国が主導して包括的な支援体制を構築し、業界全体の改革を促進する必要があったのです。ここでは、法律制定の背景となった主な課題について詳しく見ていきましょう。
01深刻化するドライバー不足
物流総合効率化法が施行された最も重要な背景の一つが、深刻化するトラックドライバー不足の問題です。 高齢化や労働環境の厳しさなどから、物流業界では慢性的な人手不足が続いていました。
特に長時間労働や荷役作業の負担、不規則な勤務体系など、トラックドライバーの労働環境は厳しく、 若年層の新規参入が進まない状況が続いていました。国土交通省の調査によれば、トラックドライバーの平均年齢は全産業平均を上回り、 高齢化が進行しています。このままでは近い将来、深刻な輸送力不足に陥ることが予想され、物流業界全体の持続可能性が危ぶまれる状況となっていたのです。
02環境問題への対応の必要性
第二の重要な背景は、環境問題への対応の必要性です。パリ協定の採択以降、CO2排出量削減は国際的な重要課題となりました。 物流分野、特にトラック輸送は温室効果ガスの排出源として大きな割合を占めており、環境負荷の低減が強く求められるようになりました。
日本の運輸部門のCO2排出量のうち、約9割が自動車から排出されており、その中でも貨物車による排出量は相当な割合を占めています。 国際的な環境規制の強化や脱炭素社会への移行が進む中、物流分野においても環境に配慮した取り組みが不可欠となり、より環境負荷の少ない物流システムへの転換が急務とされていました。
03物流コストの上昇問題
第三の背景として、物流コストの上昇問題があります。燃料価格の高騰や人件費の上昇などにより、物流コストは年々増加傾向にありました。 特に原油価格の変動は物流コストに直接影響し、経営の安定性を損なう要因となっていました。
また、ドライバー不足を背景とした人件費の上昇も、物流コスト増加の大きな要因となっていました。 これらのコスト上昇は、単に物流事業者の経営を圧迫するだけでなく、荷主企業の競争力低下や最終的には消費者物価の上昇にもつながる重要な課題でした。 効率的な物流システムの構築によるコスト削減が強く求められていたのです。
04eコマースの拡大による物流量の増加
第四の背景は、eコマースの急速な拡大による物流量の増加です。インターネット通販の普及により、小口多頻度配送の需要が急増し、物流システムに大きな負荷がかかるようになりました。
特に消費者の即日配送・翌日配送への期待の高まりは、物流事業者にとって大きな負担となっていました。 また、返品物流の増加なども含め、従来の物流体制では対応しきれない状況が生まれ、新たな効率化の仕組みが必要とされていました。 eコマース市場の拡大は今後も継続すると予想され、持続可能な物流システムの構築が急務となっています。
05物流改革の推進
これらの複合的な課題に対応するため、国は物流総合効率化法を制定し、効率的で環境に優しい物流システムの構築を促進することにしました。 特に、個々の事業者だけでは実現が難しい物流改革を推進するため、複数の事業者による連携や先進技術の導入を支援する狙いがありました。
法律の制定により、モーダルシフトや共同配送などの取り組みが促進され、物流の効率化と環境負荷の低減を同時に実現することが期待されました。 単なる規制ではなく、支援措置を通じて事業者の自主的な取り組みを促進する点が、この法律の特徴といえるでしょう。
物流総合効率化法施行による物流業界への影響

物流総合効率化法の施行は、物流業界に多大な影響を与えています。まず注目すべき影響としては、共同物流の広がりが挙げられます。 従来は各社が個別に行っていた物流業務を複数の企業が共同で行うことで、車両の積載率向上や総走行距離の削減といった効果が生まれています。
特に地方の中小物流事業者にとって、共同物流は重要な生き残り戦略となっています。単独では維持が難しい輸送ルートも、複数社が連携することで維持できるケースが増えているのです。 地域の物流ネットワークの維持・強化という面でも、法律の効果は大きいといえるでしょう。
また、モーダルシフトの進展も重要な影響です。トラック輸送から鉄道や船舶への切り替えが進み、長距離輸送の効率化とCO2排出量削減に貢献しています。 特に長距離フェリーの利用が増加し、ドライバーの労働環境改善にも寄与しています。
さらに、先進的な物流施設の整備が加速したことも大きな変化です。自動化・機械化された物流センターの導入により、作業効率の向上と労働力不足への対応が進んでいます。 特に大都市圏では、高機能な物流施設の開発が活発化し、物流不動産市場も活性化しています。
加えて、物流DXの推進も進んでいます。IoTやAIを活用した物流システムの導入が進み、情報の可視化や分析に基づく効率的な物流オペレーションが実現しつつあります。 特に需要予測や最適配車などの分野で、データ活用による効率化が進んでいるのです。
このように、物流総合効率化法は物流業界の構造改革を促進し、より効率的で持続可能な物流システムの構築に貢献しています。 特に複数事業者の連携や先進技術の導入を後押しすることで、個社だけでは実現が難しかった改革が進んでいるといえるでしょう。
物流総合効率化法施行で企業が今後取り組むべきこと

企業は、物流総合効率化法の施行を機に、まず自社の現状をしっかり把握し、業務プロセスの見直しと最新技術の導入、従業員のスキルアップを図るための体制整備を進めることが急務となっています。
また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や自動化システムの導入といった先進技術を取り入れることで、 効率性と安全性の両立を実現する具体策を確立し、企業全体の競争力を強化していく必要があります。
さらに、外部の専門家や支援制度を上手く活用し、現場での成功事例や最新の実践データをもとに、短期的な成果と長期的な成長の両面から、 継続的な業務改善に取り組むことが、今後の持続的発展につながる重要な戦略といえます。
物流業務の効率化は株式会社コモンコムへ

株式会社コモンコムは、最先端のIT技術と豊富な現場実績をもとに、各企業の業務プロセスを細かく分析し、効率化とコスト削減の両立を実現するためのオーダーメイド支援を行っています。 お客様の現状や課題をしっかりとヒアリングし、最適な改善策を提案するだけでなく、導入後のフォローアップや運用サポートにも万全の体制を整え、安心して利用できるサービスを提供しています。
信頼と実績に裏打ちされたコモンコムのソリューションは、企業の持続可能な成長を全面的にバックアップし、
次世代の物流環境の実現に向けた確かな一歩となるでしょう。
現在、株式会社コモンコムでは、無料のオンライン相談会も実施しています。 物流の効率化にお悩みの企業様は、ぜひ株式会社コモンコムに気軽に相談してみてください。
詳しくは公式サイトまで
運送システムのコモンコム
LOGI-Cube STORAGE(ロジキューブストレージ)