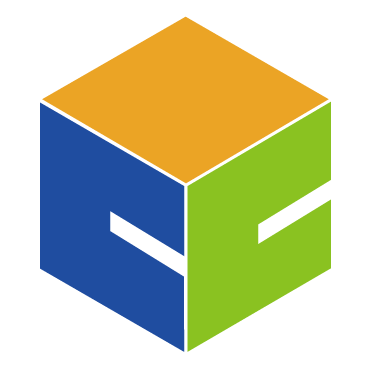自動点呼とは?
導入までの流れから2025年現在の動向と将来的なメリット・課題まで解説

2025年、運送業界では自動点呼の導入がいよいよ始まりつつあります。この技術により、運転者は国土交通省認定の自動点呼システムを活用し、従来の対面点呼と同等の安全性を維持しながら、点呼をよりスムーズかつ効率的に実施できるようになります。
自動点呼の導入には、運行管理者の業務負担軽減や労働時間短縮といった大きなメリットが期待される一方で、機器・システムの認定・申請手続きや運用体制の整備、緊急時対応を含む安全性確保などの課題もあります。
本コラムでは、2025年現在の最新動向を踏まえ、自動点呼の基本的な仕組みから導入までのフロー、業務前・業務後自動点呼の現状と将来展望、さらに助成制度情報までを詳しく解説します。運送業界における次世代の点呼方式として自動点呼に興味をお持ちの方は、ぜひご一読ください。
自動点呼とは?

運行の安全確保のために、自動車運送事業者は事業用自動車の運転者に対して、原則として対面での点呼を実施しています。 点呼では、運転者の酒気・疾病・疲労の確認やドライバーへの必要な指示を行っています。
自動点呼は、運転者がロボットや先進的なシステムを活用して行うセルフ点呼の新しい形になります。このシステムの魅力は、 何と言ってもほぼ無人での点呼実施が可能という点にあります。人が直接行っていた点呼をロボット技術を活用して実施することにより、 運行管理者の作業の負担を緩和することが期待されます。
2025年5月の情報によれば、自動点呼の導入は大きく進展しています。
- 業務後自動点呼(乗務後自動点呼)に加え、業務前自動点呼(乗務前自動点呼)も2025年4月30日の法改正により解禁され、対面点呼と同等の効果を有するものとして制度化されました。
- これにより、従来は業務後自動点呼のみが認められていましたが、現在は業務前自動点呼も認定機器・システムを用いれば実施可能となっています。
自動点呼の実施には以下の条件があります。
- 国土交通省の認定を受けた自動点呼機器・システムを使用すること。
- 自動点呼を行う際は、万が一の事態に備え、運行管理者がすぐに対処できる体制を整えておくことが求められます。
- 導入には所轄の陸運支局への正式な申請が必要です。
このような条件が設けられている背景には、運行の安全確保があります。また、全ての自動点呼機器が認定されるわけではなく、国土交通省の厳格な認定を受けた製品のみが利用可能です。
2025年5月現在、業務前・業務後どちらの自動点呼も制度上認められ、 運行管理者やドライバーの業務効率化・労働時間短縮が期待されていますが、安全性確保のための運用体制整備も引き続き必須となっています。
自動点呼以外の点呼の種類

運送業界では、自動点呼以外にも複数の点呼方式が認められています。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、 運送事業者は自社の規模や運行形態に応じて適切な方式を選択する必要があります。ここでは、現在利用可能な点呼の種類について詳しく解説します。
01対面点呼
対面点呼は、運行管理者と乗務員が直接顔を合わせて行う最も基本的な点呼方式です。運行管理者が乗務員の体調や精神状態を目視で確認し、 アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無をチェックします。表情や声のトーン、動作などから乗務員の状態を総合的に判断できるため、最も確実性の高い点呼方式とされています。
多くの運送事業者で標準的に採用されており、特に大型車両や危険物輸送を行う事業者では重要視されています。 運行管理者と乗務員の直接的なコミュニケーションにより、安全運行に関する注意事項の伝達も効果的に行えます。
02電話点呼
電話点呼は、運行管理者と乗務員が電話を通じて行う点呼方式です。遠隔地での運行開始時や営業所外での点呼が必要な場合に活用されています。 声のトーンや話し方から乗務員の状態をある程度把握できますが、視覚的な確認ができないため対面点呼と比較して情報量は限定的です。
アルコール検知については、携帯型のアルコール検知器を使用し、その結果を電話で報告してもらう形が一般的です。 緊急時や特別な運行形態において有効な手段として、多くの事業者で補完的に利用されています。
03IT点呼
IT点呼は、インターネットやテレビ電話システムを活用した点呼方式です。 パソコンやタブレット端末のカメラ機能を使用して映像と音声の双方向通信を行い、運行管理者が乗務員の状態を視覚的にも確認できます。 対面点呼に近い確認レベルを保ちながら、遠隔地でも実施可能な利便性があります。
専用のアルコール検知器と連携することで、検知結果をリアルタイムで共有できる仕組みも整備されています。 IT技術の進歩により画質や音質も向上しており、多くの運送事業者で導入が進んでいる点呼方式です。 システム導入には初期コストが必要ですが、運行効率の向上や管理業務の合理化につながるメリットがあります。
04遠隔点呼
遠隔点呼は、2022年4月から新たに認められた点呼方式で、グループ企業間での点呼業務を可能にする制度です。 運送事業者が他の営業所や関連会社の運行管理者による点呼を受けることができます。 IT技術を活用した映像・音声による双方向通信システムを使用し、アルコール検知器の結果もリアルタイムで共有されます。
運行管理者不足の解決策として期待されており、特に中小規模の運送事業者にとって有効な選択肢となっています。 ただし、実施には国土交通省への届出と一定の要件を満たす必要があり、適切なシステム構築と運用体制の整備が求められます。
乗務後自動点呼の導入までの流れ

乗務後自動点呼の導入は、段階的なプロセスを経て進める必要があります。適切な計画と準備により、スムーズな導入と効果的な運用が可能となります。
ここでは、導入検討から実際の運用開始まで、具体的な手順について詳しく解説します。
01導入する場所を決める
自動点呼システムの設置場所は、運用効率と安全性を両立できる環境を選定することが重要です。乗務員が帰庫時に自然にアクセスできる動線上に配置し、 十分な照明と静かな環境を確保する必要があります。電源設備やネットワーク環境の整備状況も考慮し、 システムの安定稼働に必要なインフラが整っているかを事前に確認します。
また、プライバシーに配慮した設置場所の選定により、乗務員が安心して点呼を受けられる環境作りが求められます。 設置スペースの確保と併せて、メンテナンスや管理のしやすさも検討要素として重要です。
複数の候補地がある場合は、運行パターンや乗務員の動線を分析し、最も効率的な場所を決定することが推奨されます。
02機種を決める
自動点呼システムの機種選定は、事業規模や運行形態に適した機能と性能を持つ製品を選ぶことが重要です。アルコール検知機能、体温測定、 血圧測定など、必要な健康チェック機能を備えているかを確認します。操作性の良さや画面の見やすさも重要な要素で、高齢の乗務員でも使いやすい設計になっているかを検討する必要があります。
データ管理機能やクラウド連携機能の有無、既存の運行管理システムとの連携可能性も選定の判断材料となります。複数のメーカーから見積もりを取得し、 初期費用だけでなく保守費用やランニングコストも含めた総合的なコスト比較を行うことが推奨されます。実機でのデモンストレーションを通じて、実際の使用感を確認することも大切です。
03届け出する
自動点呼システムの導入には、運輸支局への事前届出が義務付けられています。届出書類には、使用する機器の仕様書、設置場所の図面、運用方法の詳細などが必要です。 届出は運用開始予定日の10日前までに提出する必要があり、書類に不備があると受理されないため注意が必要です。
運輸支局の担当者と事前に相談し、必要書類や手続きの詳細を確認しておくことが重要です。
04乗務後自動点呼を開始する
システム導入後は、乗務員への操作研修と運用ルールの周知を徹底的に行います。初期運用では運行管理者が立ち会い、 システムの正常動作と乗務員の操作習熟度を確認することが重要です。データの記録・保存状況や異常時の対応手順も実際に確認し、問題があれば速やかに改善措置を講じます。
運運用開始後も定期的にシステムの動作状況をチェックし、メンテナンススケジュールに従った保守点検を実施することで、 長期的に安定した運用を維持できます。乗務員からのフィードバックを収集し、必要に応じて運用方法の見直しも行うことが推奨されます。
段階的な導入により、徐々に自動点呼の対象範囲を拡大していくアプローチも効果的です。
【2025年】業務前自動点呼の現状と動向

2025年現在、業務前自動点呼の導入検討が運送業界で活発化しています。乗務後自動点呼の普及が進む中、運行管理者不足の深刻化により、 業務前点呼の自動化に対する期待が高まっています。 国土交通省では業務前自動点呼の実現に向けた技術的な検証と法制度の整備を継続的に進めており、関係団体との協議も重ねられています。
技術面では、AIを活用した健康状態の判定精度向上や、緊急時対応システムの開発が進んでいます。運送事業者からは早期実用化を求める声が多く寄せられており、実証実験への参加希望も増加傾向にあります。 業界全体として、業務前自動点呼の実現による労働環境改善と安全性向上への期待が高まっています。
【2025年】業務前自動点呼の将来的なメリットと課題

業務前自動点呼が実現すれば、運送事業者にとって大きなメリットをもたらすことが期待されています。24時間体制での点呼が可能となり、 運行管理者の負担軽減と人手不足の解消につながります。コスト削減効果も見込まれ、長期的な経営改善に寄与することが予想されます。
一方で、乗務員の健康状態や適性の正確な判断、緊急時の対応体制など、解決すべき課題も存在しています。 技術の進歩とともに、これらの課題への対応策が検討されています。法制度の整備と併せて、安全性を確保しながらの段階的な導入が重要となります。
自動点呼システム導入の助成情報

自動点呼システムの導入には、国や地方自治体からの助成制度を活用できる場合があります。 運輸事業振興助成制度や地域の中小企業支援制度など、複数の助成プログラムが用意されています。
助成金の申請には事前の計画書提出や要件確認が必要で、導入時期や対象機器に制限がある場合もあります。 補助率や上限額は制度により異なるため、事前の詳細確認が重要です。申請手続きには専門知識が必要な場合もあり、導入業者のサポートを受けることが推奨されます。
助成制度を効果的に活用することで、導入コストの負担を軽減し、スムーズなシステム導入が可能となります。
自動点呼システムの導入なら株式会社コモンコムへ

以上が、自動点呼の現状と今後の見通しについての解説となります。 自動点呼は、運送業務の効率化や品質向上を実現するために有効な手段ですが、 導入にはコストや期間、運用や教育などの課題があります。乗務前自動点呼が今後どう展開していくのかも気になるところです。
国土交通省は、乗務前自動点呼についても実証実験含めて引き続き検討していくとしており、今後の制度化に向けた動きが2024年問題の観点からも期待されます。
業務前・業務後自動点呼について展示会を行っております。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
システムに関するお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。
Address/住所
- 〒813-0044 福岡市東区千早 5丁目13-38
ルリアン香椎参道 6階 - 092 410 5113
- info@commoncom.jp
- commoncom.jp