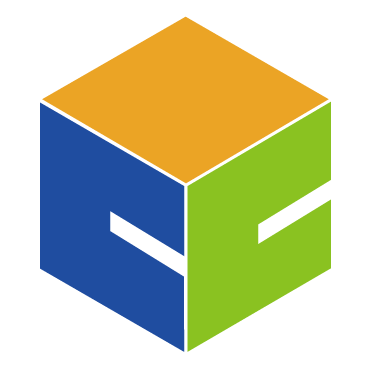倉庫保管料とは?算出の単位や計算方法・削減のための4つのポイントを徹底解説

倉庫業を営んでいる業者様向けに、世の中には数多くの倉庫管理システムが存在します。日々の入出庫を管理して在庫を把握したり、様々な関連帳票を印刷したり、ハンディターミナルなどの外部機器と連携してさらなる業務の効率化を図ったりなど、倉庫管理システムによって提供する機能は多岐にわたります。
中には入出庫の情報から保管料を計算して請求書まで発行できる機能を備えた倉庫管理システムもありますが、計算方法によっては対応できないというケースも稀にありますので、システム選定の際には注意が必要です。
-
倉庫保管料とは?
算出の単位や計算方法・削減のための4つのポイントを徹底解説 - 倉庫保管料とは?
- 保管料は物流コスト全体のどれくらいを占めている?
- 保管料算出の単位
- 保管料を算出する計算方法
- 保管料削減のための4つのポイント
- 保管料の値上げ傾向への対策
- 保管料の勘定科目
倉庫保管料とは?

倉庫保管料とは、企業が倉庫に資材や商品を預ける時に発生する費用のことです。
保管料は保管する資材や商品の大きさや量、保管期間に基づいて計算されるようになっていますが、提供されるサービスや倉庫の立地などによって、 より細かな料金が異なってきます。医薬品や温度・湿度を一定にキープする必要がある食品などは一般倉庫ではなく危険別倉庫などに保管する必要が出てくるため、 一般的な資材・商品と比較すると一層高い保管料がかかる場合もあります。
保管料は物流コストを構成する重要な要素の1つにもなっています。利用の仕方次第でコスト削減や効率的なスムーズな在庫管理に直結するため、 企業が物流戦略を立てる時には保管料の最適化が特に重要です。
保管料は物流コスト全体のどれくらいを占めている?

物流コストは保管料と作業料、配送料の3種類で大きく構成されていて、その構成比は 保管料が15%、作業料が25%、配送料が60%と言われています。 特に保管料を細かく見ていくと、製造業が約16%、非製造業が約14%、卸売業が約16%、小売業が約10%の値になっています。
作業料と配送料と比較すると割合は小さいですが、ビジネス規模が大きい場合であれば保管料の見直しにより大きなコスト削減につなげることができるため意識しておきましょう。
また保管料は保管する商品の種類や倉庫の契約方法などにより、発生する費用に差が出る場合もあります。そのため商品の種類や契約方法も一度見直してみることがおすすめです。
保管料算出の単位

そもそも営業倉庫とは、物流サービスを提供する企業が所有・運営する倉庫で、他の企業から荷物を預かって保管・出荷するサービスを行っています。営業倉庫を利用することで、自社で倉庫を持つ必要がなくなり、物流コストや在庫管理の負担を軽減することができます。
しかし、営業倉庫を利用する際には、倉庫料と呼ばれる費用が発生します。倉庫料は、一般的に保管料と荷役料に分けられます。保管料とは、倉庫に荷物を預ける期間に応じて発生する費用で、荷物の種類や数量・サイズ・重量などによって異なります。
一方、荷役料とは荷物の入出庫時に発生する費用で、作業量や作業時間などによって異なります。 営業倉庫における保管料の計算方法には、様々な種類がありますが、まず保管料算出の単位として代表的な以下の5つを紹介します。
01個建て
個建てとは、預けたい荷物のサイズがほぼ均一である場合に用いられる計算方法で、荷物1個あたりの単価が設定されており、実際に倉庫に預けた個数に単価を掛けて保管料を算出します。
個建てのメリットとしては、荷物の数量が明確なため保管料の計算が簡単でわかりやすいという点です。対してデメリットとしては、荷物のサイズや形状が異なる場合は倉庫内に無駄なスペースが生じてしまうため効率が悪くなる可能性があるということです。
02坪建て(坪貸し)
坪建て(坪貸し)とは、使用する坪数がベースとなる計算方法です。どのような荷物でも柔軟に対応可能で、メジャーな契約形態の1つと言えます。坪建ての契約には、都度使用した坪数分を請求する「使用坪契約」や、あらかじめ使用する坪数を算出してから坪数を固定する「固定坪契約」などがあります。1坪当たりの単価が定められており、その単価に使用した坪数を掛けて保管料を計算します。坪建てのメリットとしては以下のような点が挙げられます。
- 荷物のサイズや形状に関係なく、必要なスペースだけ借りることができる。
- 使用坪契約の場合、荷物の入出庫に応じて保管料が変動するため、無駄なコストを抑えることができる。
- 固定坪契約の場合、予め決まったスペースを確保できるため、在庫管理がしやすい。
一方、デメリットは以下のような点が挙げられます。
- 荷物の数量や重量に関係なく、スペース単位で保管料が決まるため、空間効率を考慮する必要がある。
- 使用坪契約の場合、荷物の入出庫に応じて保管料が変動するため、予算管理がしにくくなる恐れがある。
- 固定坪契約の場合、予め決めたスペースよりも多くの荷物を預けることができないため、柔軟性に欠けることがある。
03パレット建て
物流業界では荷物を載せる板状の荷役台をパレットと呼びますが、一般的には、フォークリフトの差し込み口がついていて、平らな形のものを指します。パレット建てとは、このパレット1つあたりで保管料を算出する方法です。預ける荷物をパレット単位で大量に出荷したりする場合は、このパレット建てが利用されることもあります。パレット建てのメリットは、荷物が既にパレットに乗っているため、荷役作業が効率化されるという点です。
一方デメリットは、パレットに乗せる荷物の重量や高さに制限があるため、柔軟性に欠ける可能性がある、また上部に余剰スペースが発生することがあるという点です。
→「ハンディターミナル導入で劇的効率化~倉庫業務のピッキング作業効率化について~」
04重量建て
重量建てとは、商品サイズではなく預けた荷物の重量に応じて保管料を算出する方法で、液体や穀物など荷物の重量が大きく変動する場合や、サイズに比べて重量が大きくなる場合に適しています。重量建てのメリットは重量の正確な計測がしやすく保管料の計算がわかりやすいという点ですが、倉庫によっては耐荷重制限により保管できる量に制限がある場合もあるため注意が必要です。
05容積建て
容積建てとは、預けた荷物の容積(縦×横×高さ)に応じて保管料を算出する方法で、一般的には海外からの輸送など、コンテナを使用した荷物の場合によく用いられます。1立米(m3)当たりの単価が設定されており、その単価に預けた荷物の総容積を掛けて保管料を計算します。
容積建ては先にも述べたようにコンテナなどを使用した荷物に利用されますが、コンテナはある程度サイズが一定に決まっているため、坪建てやパレット建てで生じる無駄なスペースが発生しにくく、効率的な保管が可能な点がメリットと言えます。一方でコンテナの移動には特別な設備や操作が必要となるため、保管料だけでなく設備使用料や作業料などの費用が別途発生する可能性もあります。
保管料を算出する計算方法

ここまで保管料の計算単位について述べてきましたが、計算単位とは別に、保管料を算出する計算方法が存在します。今回はメジャーな計算方法を3つご紹介します。
01一期制
一期制とは、1ヶ月単位で保管料を算出する方法で、保管料は、「月初在庫数 + 月間入庫数」で求められます。複雑な計算式や日割り計算などが不要なため、保管料の計算が簡単でわかりやすいというメリットがあります。一方、在庫量が減っても保管料が変わらないことがデメリットと言えるため、一期制は入出庫があまり多くない在庫量が安定している商品や、入出庫のタイミングが不定期な商品に向いていると言えます。
02二期制
二期制とは、1ヶ月を1日から15日までと16日から末日までの2つの期間に分けて保管料を算出する方法で、保管料は「上期保管積数 + 下期保管積数」で求められます。上期保管積数とは、「繰越在庫 + 上期入庫数」で求められ、下期保管積数とは、「中間在庫 + 下期入庫数」で求められます。以下に具体例を記載します。
- 期毎の保管料単価:100円
- 上期→繰越在庫:50個 入庫数:10個 出庫数:20個
- 下期→中間在庫:40個 入庫数:50個 出庫数:20個
この場合、各期の保管料は次のようになります。
- 上期→(50+10)×100=6,000円
- 下期→(40+50)×100=9,000円
以上のように下期の出庫数は当月の計算には影響せず、翌月の繰越在庫に影響するというのがポイントです。一カ月の保管料としては上期の「6,000円」と下期の「9,000円」を合計した「15,000円」となります。 二期制は、次に記載する三期制よりも入出庫のタイミングに左右されにくく、一期制よりは入出庫のタイミングに影響されるという特徴があります。主に冷凍・冷蔵倉庫で採用されること多い計算方法です。
03三期制
三期制とは、物流業界における保管料の計算方法として最もポピュラーなもので、1ヶ月を「1日~10日」「11日~20日」「21日~末日」の3つの期間に分けて、倉庫の保管料を算出する方法です。保管料は、一期制、二期制と同じく「保管積数 × 保管料単価」で求められますが、区切りが多くなる(前期、中期、後期や1期、2期、3期など呼び方は会社によって様々)のが主な違いです。具体例は以下の通りです。
- 期毎の保管料単価:100円
- 1期→繰越在庫:30個 入庫数:20個 出庫数:40個
- 2期→繰越在庫:10個 入庫数:30個 出庫数:20個
- 3期→繰越在庫:20個 入庫数:50個 出庫数:30個
この場合、各期の保管料は次のようになります。
- 1期→(30+20)×100=5,000円
- 2期→(10+30)×100=4,000円
- 3期→(20+50)×100=7,000円
以上のように、一カ月の保管料としては1期の「5,000円」、2期の「4,000円」、3期の「7,000円」を合計した「16,000円」となります。 三期制では一期制や二期制に比べると入出庫のタイミングに影響されやすいという特徴がありますが、タイミングをうまく調整することで保管積数を抑えることができるため、同じ入出庫回数であっても三期制の方が保管料が安くなるというメリットがあります。
保管料削減のための4つのポイント

ここからは保管料削減のための4つのポイントを紹介します。ただ漠然と行動するだけではなかなか保管料の削減に繋げられないですが、4つのポイントを意識して行うだけで全く違ってくるためぜひ参考にしてみて下さい。
01在庫の最適化
1つ目のポイントは在庫の最適化です。需要予測の精度を上げて過剰在庫を削減することで保管スペースを縮小できるようになります。 季節商品の出荷計画を前もって立てることで、保管期間を最小限に抑えることも可能です。他には単純に保管方法を見直すことも有効で、少なからず効果を期待できます。
02最適な倉庫選びと契約方法の見直し
2つ目のポイントは最適な倉庫選びと契約方法の見直しです。立地や設備、商品の多さなどによって最適な倉庫は異なってくるため、 倉庫選びも重要なポイントになってきます。最適な倉庫を見つけられれば、お金を無駄にせずに済む上に商品の保管もよりスムーズにできるようになります。
契約方法も今一度見直してみることもおすすめです。見直すことで必要以上に払い過ぎていたことやコストカットできる事などが出てくる場合があります。
033PLの活用
3つ目のポイントは3PLの活用です。3PLとはThird Party Logisticsの略称で、外部の専門業者に企業の物流業務を委託するサービスのことです。3PLを利用することで スケールメリットを生かしたコスト削減をできるようになったり専門性の高いサービスを受けられたりする場合があります。
04パレットの効果的な活用
4つ目のポイントはパレットの効果的な活用です。パレットにもさまざまな素材、サイズのものがあり、種類が豊富です。 倉庫の設備や商品の特性に合わせたものを選ぶことで使いやすさが増すため、どのパレットを選ぶかも非常に重要です。
最近ではパレットのレンタルやサイクルシステムなどもあり、それらを活用することでコスト削減に繋げることができるためぜひ生かしてみて下さい。
保管料の値上げ傾向への対策

最近ではeコマースの拡大に伴って、素早い配送をするために都市近郊の小規模倉庫の需要が高まりつつあります。このことで従来の大規模倉庫と比較して高い保管料が発生する可能性があります。 その対策としては長期契約をすることで料金の固定化を狙うことです。料金が固定化されていると上がることが基本的にないため安心して続けて払いやすいです。
また季節変動を考えた柔軟な契約や色々な倉庫を使い分けるマルチ拠点戦略などもおすすめです。その時の状況や保管する商品によって上手く活用していきましょう。 他には自動化技術を導入すること、AIやIoTを採用した在庫管理システムを利用することなども考えられるためそちらにも注目です。
保管料の勘定科目

適切な勘定科目の選択は、財務諸表を作成したり税務申告をしたりする際に必要不可欠なため倉庫保管料も適切に勘定科目の選択をしましょう。 一般的に倉庫保管料は倉庫料や保管料という勘定科目で処理されるようになっています。 倉庫料や保管料の勘定科目は通常だと損益計算書上で販売費及び一般管理費に分類されます(企業の業種や取引の性質などによっては、異なる処理が必要な場合もあり)。 商品の仕入れに直接関連している保管料は仕入諸掛として処理もできます。
物流業務の効率化なら株式会社コモンコムへ

以上が、営業倉庫における倉庫料の計算方法の例です。多種多様な計算方法があるため、取り扱う荷物の種類や自社の設備を考慮したうえで、利益が最大となる計算方法を選択することが重要です。また、倉庫管理に特化したシステムを使用する場合は、自社の保管料計算方法に対応しているのか、対応していないのであればカスタマイズはできるのかなどにも注意して選定しましょう。
弊社コモンコムでは倉庫業向けシステム「LOGI-Cube STORAGE(ロジキューブストレージ)」や、ハンディターミナルのご提案も行っています。お気軽にご相談ください。
LOGI-Cube STORAGE(ロジキューブストレージ)
お問い合わせフォーム
システムに関するお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。
Address/住所
- 〒813-0044 福岡市東区千早 5丁目13-38
ルリアン香椎参道 6階 - 092 410 5113
- info@commoncom.jp
- commoncom.jp