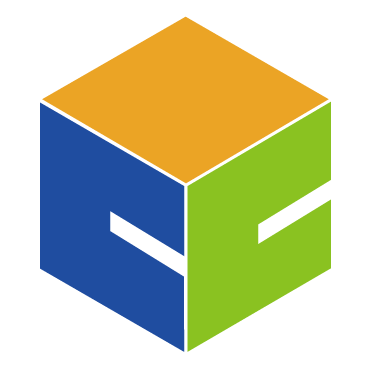モーダルシフトが進まない理由を解説!導入によるメリットや2024年問題に対して取り組むべきこととは?

近年、物流業界を中心に注目を集める言葉があります。それが「モーダルシフト」です。「モーダル」は「モード」や「方法」を意味し、「シフト」は「変更」や「移行」を指します。モーダルシフトとは、簡単に言うと、貨物輸送の方法を変更・移行することを意味しています。
具体的には、トラックなどの陸上輸送を主体としていた貨物輸送を、より環境に優しい海上や鉄道輸送へとシフトさせる取り組みのことを指します。この背景には、環境問題への対応や労働環境の改善、さらには物流の効率化といった多岐にわたる課題が絡んでいます。このコラムでは、モーダルシフトの可能性と課題について詳しく解説していきます。
-
モーダルシフトが進まない理由を解説!
導入によるメリットや2024年問題に対して取り組むべきこととは? - 2024年問題とは?
- モーダルシフトの導入による4つのメリット
- モーダルシフトが進まない理由
- モーダルシフトへの支援措置を定めた政策
- モーダルシフト加速化緊急対策事業費補助金
- モーダルシフト戦略において物流事業者が取り組むべきこと
- モーダルシフトの企業の取り組み事例4選
- まとめ
2024年問題とは?

物流業界にとって、2024年は大きな転換点となる年でした。なぜなら、2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の罰則付き規制が適用されたからです。
この規制は、働き方改革関連法の一環として2019年に施行されたものです。一般の労働者には年間720時間の残業上限が設定されていますが、ドライバーについては2024年までの猶予期間が 設けられていました。
この規制により、物流業界はどのような影響を受けるのでしょうか。まず、トラックで長距離輸送を行っている事業者は、ドライバーの労働時間を短縮する必要があります。
しかし、ドライバー不足や荷物量の増加などの現状を考えると、これは容易なことではありません。あるシンクタンクの試算によると、全国平均で、ドライバー数ベースで25年に28%、30年には35%の荷物を運びきれなくなる可能性があるとされています。
また、残業時間が減少することにより、ドライバーの給与も減少することが予想されます。これは、ドライバーの離職率を高める要因となります。
さらに、ドライバーを確保するために給与を引き上げることになれば、陸上輸送費も上昇することになります。これらの影響は、物流業界だけでなく、荷主や消費者にも波及することでしょう。
このように、2024年問題は物流業界にとって深刻な課題ですが、それを解決するための有効な手段の一つがモーダルシフトなのです。
モーダルシフトの導入による4つのメリット

それでは、モーダルシフトを導入することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか? ここからは、モーダルシフト導入によるメリットを4つ紹介します。
01ドライバー不足の解消
先ほども説明したように、働き方改革の一環として、2024年4月から自動車運転業務にも労働時間の上限規制が施行されました。 それに伴い、労働力不足が懸念されることになりますが、モーダルシフトの「大量輸送」は大量の貨物を少ない人員で一度に運ぶことを可能とし、 結果として輸送効率を高める事に繋がるのです。
02CO2排出量の削減
国土交通省が公開している資料によると、1トンの貨物を1㎞輸送する際に発生するCO2排出原単位は、営業用貨物車の216に対し、船舶は43と規定されています。 つまり、陸上輸送を海上輸送に切り替えることで、CO2を約80%削減することが可能です。鉄道輸送でも同様にCO2削減効果が期待できます。
03輸送コストの低減
海上や鉄道輸送では、一度に多くの貨物を運ぶことができます。例えば海上輸送ではフェリーシャーシと呼ばれる着脱可能な車両を利用し、海上輸送区間ではドライバーが運転する必要がありません。 これにより、ドライバーの労働時間や燃料費などの輸送コストを削減することができます。
04輸送品質の向上
海上や鉄道輸送では、天候や交通事情などの影響を受けにくく、定時性に優れています。また、荷物の損傷や紛失などのリスクも低減されます。これにより、荷主や消費者の満足度を高めることができます。
モーダルシフトが進まない理由

モーダルシフトは、2024年問題だけでなく、環境問題や物流効率化などの観点からも有効な対策です。ところが、その必要性に迫られながらも、スタンダードな運送方法として広く普及しているかと言うとそうとは言えないのが現状です。
例えば鉄道輸送の場合、一般的に500キロメールを超えると輸送料金はトラックよりも割安になるとされ、東京・福岡間(約1100メートル)など長距離では優位であるはずが、今なお貨物の輸送形態別シェアは5%程度にとどまっているのが現実です。
背景には融通が利きづらい固定ダイヤや、トラックへの積み替えの煩わしさ、近年では台風や大雨による大規模災害による運休など、デメリットやネックとなりうる要素が多いことが挙げられます。その他にもモーダルシフトを推進していくためには、以下のような課題を克服する必要があります。
01大規模災害の影響を受けやすい
導入が進まない最大の理由は、大雨や雪などの天候や自然災害によって輸送の確実性が低くなることにあります。 天候による遅延はトラック輸送でも同じリスクがあると考えやすいですが、 影響の範囲が大きく異なります。大きな影響が出てしまう理由としては、「輸送する貨物」、「輸送ルート」、「運行ダイヤ」等の要因が考えられます。
02輸送時間の長さ
海上や鉄道輸送は、陸上輸送に比べて輸送時間が長くかかる場合があります。特に海上輸送では、港湾での荷役や船舶の運航スケジュールなどにより、 輸送時間が変動する可能性があります。これは、荷主や消費者の納期や在庫管理に影響を与えることになります。
03輸送ネットワークの不足
海上や鉄道輸送は、陸上輸送に比べて輸送ネットワークが限られています。特に鉄道輸送では、貨物駅やコンテナターミナルなどの物流施設が不足している場合があります。 これは、荷主や物流事業者の利便性や柔軟性を低下させることになります。
04 輸送体制の変更
海上や鉄道輸送は、陸上輸送とは異なる輸送体制を必要とします。例えば海上輸送では、フェリーシャーシやコンテナなどの専用の機材を用意する必要があります。 また、海上や鉄道輸送では、陸上との接続性や情報連携などを確保する必要があります。これは、荷主や物流事業者にとってコストや手間がかかることになります。
05ラストワンマイルへの対応
ラストワンマイルとは、配達店などの最終拠点から、お客様に荷物をお届けするまでの区間を指します。 トラック輸送であれば、大都市間の長い距離を走行する幹線輸送と、ラストワンマイルの両方の輸送に対応することができます。一方で、鉄道・船舶での輸送は、「駅から駅の間」、「港から港の間」のみの輸送となるため、臨機応変に対応しにくいと言えます。 またトラック輸送に比べ、専門的な技術が必要なため、人材確保や、育成が難しいのも課題です。
モーダルシフトへの支援措置を定めた政策

内閣府が中心となって進めている「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」では、 2023年2月に「2030年度に向けた政府の中長期計画」を公表しました。その中では「多様な輸送モードの活用推進」が掲げられており、3つの施策について触れています。
幹線輸送で多用される大型トラックと互換性の高い31ftコンテナの利用に注目が集まっています。この31ftコンテナは鉄道輸送で使用されるもので、 標準仕様パレット(T11型)積載時のスペースの無駄が少ないという特徴を持ち、「モーダルシフト推進・標準化分科会」も導入促進が望ましいと判断しています。 また、主に海上輸送で活用される40ftコンテナも中長期的な利用拡大が提唱されています。
「新しい道路規格の整備」といったアプローチでのモーダルシフトの推進の取り組みもなされています。自動物流道路がその1つであり、同時にトラック輸送から鉄道や船舶へのモーダルシフトをサポートする存在としても捉えられています。 この「自動物流道路」では、荷姿が標準化された荷物が物流専用空間内を通過し、交通インフラ(港湾・空港・鉄道など)と連携される想定がされています。
政府施策の中には自動運航船に関わるものも含まれています。既に2016年から自動操船・遠隔操船・自動離着桟といった各機能の開発・実証が進められてきましたが、 政府と船舶関係者で組織された「自動運航船検討会」において、2030年頃までの本格的な商用運航の実現を目指しています。
モーダルシフト加速化緊急対策事業費補助金

また、新たに「モーダルシフト加速化緊急対策事業費補助金」の予算措置も実施されました。
補助対象事業者の要件は「物流総合効率化法」と同様ですが、コンテナラウンドユース等の先進的なモーダルシフトに取り組む場合、 関連する機器(荷役機器や輸送機器等)の導入等を行う実証事業に必要な経費の一部が補助されます。
補助上限は鉄道輸送が3億円、船舶輸送が1億円となっており、補助率は1/2以内と定められています。
モーダルシフト戦略において物流事業者が取り組むべきこと

モーダルシフト戦略が進む中で、物流事業者が取り組むべきことは何でしょうか? ここからは、政策的支援の活用も視野に入れながら、物流事業者に必要なことを見ていきましょう。
01技術革新の導入準備
政府は自動物流道路や自動運航船などの新しい技術の実用化に向けて積極的に動いています。 物流事業者としてもこのような新技術の動向にはアンテナを張り、他の物流事業者に先駆けてサービス展開できるように実証事業に参加する等、事前に準備しておくのが望ましいと考えられます。
02荷主の業界と物流業界での連携強化
モーダルシフトの政策支援措置は荷主および物流事業者の協力が要件とされます。 輸送条件の見直し等を行うことでモーダルシフトを実現できるケースもあります。荷主の業界と物流業界での連携の可能性を模索し、互いに協力し合うことが重要です。
また、異業種の輸送案件を組み合わせることでモーダルシフトが成立する可能性もあります。物流事業者が業界間の協力強化を主導することができれば、 荷主にとっても付加価値の高い提案だとみなされます。
モーダルシフトの企業の取り組み事例4選

それでは実際に、企業はモーダルシフトをどのように取り入れているのでしょうか?
ここからは、その事例を紹介していきます。
01スズキ株式会社
自動車メーカーのスズキでは2023年4月から静岡県浜松市の本社から福岡までの部品輸送において鉄道輸送を強化しており、 現在の2〜3割程度の鉄道輸送比率を4割程度に引き上げる計画としています。
02JR九州
JR九州では「はやっ!便」というサービスを提供しています。 「はやっ!便」は2021年5月からサービスを提供していました。しかし、これまではみどりの窓口に持ち込まれた荷物を配送する宅配便に近い形態だったものが、 2023年7月からは集荷・配送までをプラスしたものへサービスを拡大したのです。モーダルシフトを推進する体制が着実に整ってきていると言えます。
03味の素株式会社
味の素株式会社では、国内食品生産の体制を再編成することに合わせ、物流ネットワークも新しくしました。 具体的には、生産拠点の三重から東北への輸送を、すべてトラック輸送からフェリーによる海上輸送に変更したという取り組みです。
このモーダルシフトにより、CO2排出量は従来よりも73.8%削減し、1輸送あたりのドライバーの労働時間を88%削減しました。国土交通省が実施した令和4年度の海事局長表彰にて、 海運モーダルシフト大賞を受賞しています。
04 ネスレ株式会社
ネスレ株式会社では、従来のトラック輸送を鉄道コンテナ輸送に切り替えるモーダルシフトを行いました。 具体的には、関東の工場から新潟の顧客まで、ペットボトルコーヒー飲料のトラック輸送を、鉄道コンテナ輸送に切り替えた取り組みです。
ネモーダルシフトにより、CO2排出量は年間で21.9トン、従来よりも88%削減し、トラック輸送台数は30台削減する効果が出ています。 令和3年度のグリーン物流パートナーシップ会議において、経済産業大臣賞も受賞しています。
物流業務の効率化は株式会社コモンコムへ

モーダルシフトは、物流業界の未来を形成するための鍵となる取り組みなのは間違いありません。 しかしながら、モーダルシフトの実現は、法的な整備や仕組み、設備を変える必要もあるため、本格的な陸送からの転換に至るにはまだまだ困難な状況です。これまでの輸送方法と組み合わせながら共存していくことが現実的なところでしょう。
モーダルシフトは2024年問題を乗り越える一つの手段となり、物流業界の将来性や競争力を高めることができます。今後も法整備や各社の取り組みを注視していきましょう。
弊社商品「LOGI-Cube」の日計表入力は面倒なインボイスも簡単、スムーズに対応できます。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
システムに関するお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。
Address/住所
- 〒813-0044 福岡市東区千早 5丁目13-38
ルリアン香椎参道 6階 - 092 410 5113
- info@commoncom.jp
- commoncom.jp