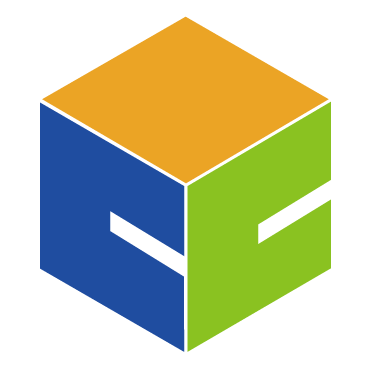430休憩とは?ルールや2024年4月からの法改正・遵守のポイントを徹底解説!

430(ヨンサンマル)休憩とは「業務の中で運転を4時間以上行う場合、30分以上の休憩をとらなければならない」というドライバーの労働・休憩時間に関する規定の通称です。
2024年4月から、この430休憩に関する「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の内容が一部改正・適用されました。
特に長距離を運転するドライバーにとって、改正後の連続運転時間と休憩時間の取り方の規定について、正しい知識を押さえることはとても大切です!
本記事では、
- 430休憩の改正のポイント
- 430休憩の対象について
- 違反した場合の罰則や想定されるトラブル
- 430休憩の遵守のために準備するべきポイント
などのトピックスについて掘り下げ、分かりやすく解説しています。
430休憩について正しく理解したい企業担当者や長距離ドライバーの方は、ぜひ参考にしてください!
430休憩とは?

430休憩とは 「4時間以上の運転をする場合、30分以上の休憩を取ること」というルールの通称です。
運転者は以下の3つのポイントを守る必要があります。
- 連続運転時間は4時間が限度
- 4時間ごとに合計30分以上の運転の中断と休憩が必要
- 休憩は分割可能(ただしおおむね連続10分以上)
これは厚生労働省による「改善基準告示」の規定により、 トラックやバスなどの運転手の長時間運転による健康被害の予防と安全確保を目的に定められました。
それではここからは、430休憩の基本的な情報と目的、規定の対象者について詳しく押さえていきましょう!
01430休憩は厚生労働省が定めた規定
この430休憩は、厚生労働省が定めた改善基準告示(正式名称:「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」)の内容の一つです。
この改善基準告示は、2022年に自動車運転者の健康確保を目的に見直しが行われ、2024年4月から休息に関する項目(430休憩)などの内容が改正、適用されました。 長距離運転者が適切な休憩を取ることは、ドライバーの心身の健康を守るためだけでなく、重大な交通事故を防ぐ上でも重要であるためです。
注意したいのは、この規定は法律ではなく、厚生労働大臣の「告示※」であることです。 そのため、もし違反しても罰則はありません。 ただし、違反が確認された場合は、企業の自主的な改善を促すための指導が行われる場合もあります。
※引用「国家や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせること。また、そのもの。」(参考:デジタル大辞泉)02430休憩の対象者
430休憩を守る必要があるのは、トラック運転手やバスのドライバーなど、 企業に雇用されており、運転を主な業務としている労働者です。
改善基準告示では、430休憩の対象者を次のように規定しています。
つまり、業務時間のほとんどを運転時間に当てている人が対象となります。
「自動車の運転業務に主として従事する者」と判断される条件は以下の通りです。
- 人や物を運ぶために自動車を運転する時間が労働時間の半分を超えていること
- かつ、この業務に充てる時間が、年間総労働時間の半分を超えると見込まれること
上記の条件を満たす場合は、個人事業主にも430休憩が適用されます。
個人事業主は労働基準法上の「労働者」には当てはまりませんが、 道路運送法と貨物自動車運送事業法等の関連法令に基づき、実質的には430休憩の規定を守ることが求められるためです。
まとめると、以下の条件を満たす場合430休憩を遵守しなければいけません。
- 企業に雇用されている労働者(ただし個人事業主にも適用される)
- トラック(営業用・自家用含む)、バス、ハイヤー・タクシーなどの運転を主な業務とする人
- 勤務時間の半分以上を人や物を運ぶ運転業務に充て、かつ年間労働時間の半分以上をその業務に充てると見込まれる人
03430休憩の目的
改善基準告示に430休憩のルールが組み込まれた背景には、 自動車運転者の長時間労働を是正し、事故を未然に防ぐためという目的があります。
運送業では、長時間労働が大きな課題とされてきました。特に「脳・心臓疾患」による労災支給決定件数は全業種中で最も多く、2021年度の運輸業・郵便業の件数は59件となっています。
この状況を踏まえて、改善基準告示の改正では、労働者の健康を守るため自動車運転者の働き方の見直しが行われたのです。
さらに長時間にわたる連続運転は、注意力の低下や疲労による眠気を引き起こします。 これらの症状は安全な運転を妨げ、事故につながるリスクを高めます。
もし、連続運転による過労が原因で、死傷者を出すような交通事故が発生したらどうでしょう。 ドライバーだけでなく、企業も責任を問われる可能性が高くなります。
運転者の過労による健康被害を予防し、交通事故による被害や損害を未然に防ぐためにも、430休憩のルールを徹底することはとても重要です!
430休憩のルールを詳しく解説

430休憩を正しく理解する上で、連続運転時間と休憩についての考え方はとても重要です。 しかし、改善基準告示の内容は複雑な言い回しが多く、分かりにくいと感じている方もいるのではないでしょうか?
ここからは、以下の430休憩のルールのポイントについて詳しく説明します。
例を挙げながらかみ砕いて説明していきますので、参考になれば嬉しいです。 それでは、430休憩のルールについて順に見ていきましょう!
01連続運転時間の上限は4時間
430休憩の規定では、運転者の連続運転時間の上限を「4時間」と定めています。 そのため、ドライバーが連続して運転する時間は原則4時間以内に収めなければなりません。
運転開始から4時間以上運転する場合には、4時間以内または4時間を超えた直後に速やかに運転を中断し、30分以上の休憩を取る必要があります。
例として、合計で5時間半運転しなければならない場合を考えてみましょう。この場合、最初に3時間半運転した後、30分の休憩時間を挟み、その後2時間運転することで、連続運転時間の上限を超えないように調整できます。
また、 休憩時間は分割して取っても構いません。
ただし、分割して休憩を取る場合、1回当たりおおむね連続10分以上を確保する必要があります。1回10分未満の休憩を3回以上連続して取った場合は、規定違反となるため注意しましょう。
この430休憩の連続運転時間のルールを遵守することで、運転者自身の過労を防ぐだけでなく、他の道路利用者の安全を守ることに繋がります。
02連続運転時間を超過した場合の罰則はない
もし4時間以上連続して運転を続けた場合でも、法的な罰則を受けることはありません。 それは430休憩の規定が「告示」であり、法律ではないからです。
ただし、企業には従業員の労働時間と休憩時間を管理する責任があります。基準告示の違反がきっかけで、 労働基準監督署の指導や、車両の使用停止などの行政処分を受ける可能性があるため、注意が必要です。
罰則がないとはいえ、430休憩の規定を守ることは、企業の信頼性や労働者の健康を守ることに直結します! 日頃から430休憩のルールを意識して業務に当たることができるよう、企業は雇用者への情報共有を心がけましょう。
03「おおむね連続10分以上」の意味
改善基準告示の430休憩の内容の中に、以下の文言があります。
この430休憩のルール改正のポイントのひとつである「おおむね連続10分以上」の意味を確認しておきましょう。
この「おおむね連続10分以上」とは、原則として10分以上の休憩を取ることが求められているものの、10分にわずかに満たない場合については例外として認められる、という意味です。
例えば、1回8分や9分の運転の中断は休憩として認められます。しかし、中断した時間が1回5分の場合は休憩として認められないとされています。
また、基本的に休憩時間は30分以上確保することが前提です。そのため、10分に満たない運転の中断が3回以上続いてしまった場合、休憩とみなされず規定違反となるので注意してください。
この改正は、休憩時間が10分にやや満たない場合ただちに違反とするのは、運転者の勤務実態に合わないと判断され、改正により見直されたものです。
繁忙期などの長時間の休憩時間の確保が難しい場合も、この430休憩のルールを意識した運行計画を立てるようにしましょう。
430休憩の2024年からの法改正3つのポイント

430休憩のルールは2024年4月から適用されましたが、具体的にはどのような内容が変更されたのでしょうか。 ここからは、改正後の規定のうち必ず押さえておきたい430休憩の3つのポイントを解説します。
改正されたポイントは以下の3点です。
それでは順に見ていきましょう。
01明確な休憩が求められる
改善基準告示の改正後は、運転の中断時に「明確な休憩」を取ることが求められるようになりました。
改正後の規定では「中断時には、原則として休憩を与えなければなりません。」 (参考:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント )と定められています。 これは、運転者は特別な事情がない限り、荷物の積み下ろしやトイレ休憩などを含まない「休憩」を30分以上取得する必要があるということです。
一方で、改正前は「運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しなければなりません。」 (参考:厚生労働省 改善基準のポイント)とされていましたが、「休憩等」の具体的な内容について記載がありませんでした。
その結果、運転の中断している時間が荷物の積み下ろし作業などに当てられ、休憩時間が十分確保できていないという事例が多く見られました。
ドライバーは、430休憩に基づいて運転を中断する際は、しっかりと体を休めるようにしましょう。企業は運転者が適切な休憩が取れるよう、効率的な運行計画を作成することが求められます。
024時間以上運転しなければならない場合は延長可能
430休憩のルールでは、連続運転時間の上限は4時間と定められています。 ただし、やむを得ない事情で4時間を超える場合は、例外的に4時間半まで延長することができます。
例えば、以下のような事情がある場合は運転時間の延長が認められます。
- 渋滞などにより4時間以内に駐車施設へ入れない
- 駐車施設に到着したものの、安全に駐停車することができない
ただし、連続運転時間の延長はあくまで例外的な措置です。
ドライバーは、休憩を確保できないと判断したら速やかに管理者へ報告し、休憩可能な場所に到着次第しっかりと休憩を取りましょう。また、管理者と運転者は日頃から休憩場所や渋滞情報を共有しておくように心がけることが大切です。
03場合によっては10分未満の休憩が認められる
430休憩の規定では、30分以上の休憩時間を分割して取る場合、基本的に休憩は1回おおむね連続10分以上でなければなりません。
「1回おおむね連続10分以上」というのは、10分にわずかに満たない場合も例外的に休憩とみなすという意味です。 例えば、やむを得ず休憩時間が8分しか取れなかった場合も、休憩として認められます。
ただし、10分に満たない休憩が、3回以上続いた場合は430休憩の規定違反となります。 10分未満の休憩は2回までとしなければならず、その後は必ず合計30分以上を満たすよう休憩時間を確保しなければいけません。
例えば、4時間以上の運転中に①9分、②9分、③8分と3回に分けて休憩を取ったとしましょう。この場合、③の8分の休憩を取った時点で430休憩の規定違反になります。このケースでは、③の休憩は少なくとも12分以上取る必要があります。
30分以上の休憩時間の確保が難しい場合、運転者の疲労にともなう注意力の低下を防ぐためにも、こまめな休憩を取ることは非常に重要です!
企業はこの際に以上で記載したルールを守ることができるよう、常日頃からこの430休憩の規定について従業員に周知するようにしましょう。
430休憩を守らなかった場合に想定される3つのトラブル

改善基準告示に法的な拘束力はなく、違反しても罰則を受けることはありません。しかし、430休憩の規定を遵守しないことで、思わぬ問題が生じる可能性があります。
ここからは、次のような430休憩のルールを守らなかった場合に発生しうるトラブルについて、掘り下げていきたいと思います。
それでは、ひとつずつ確認していきましょう!
01疲労等が原因で事故の危険が高まる
運転手が休憩を取らず長時間連続して運転を行った場合、過労による注意力散漫や眠気などが生じ、重大な交通事故を引き起こす危険性が高まります。
企業には、労働者が安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする安全配慮義務が課せられています。 (参考:労働契約法) もし重大な交通事故が発生し、運転手に適切な休憩を取らせなかったことが管理者の責任であると認められた場合、企業が損害賠償を請求される可能性も十分にあります。
そのためにも、まずはドライバー自身が430休憩のルールを理解し、意識して業務に取り組むことが大切です。そして企業は休憩時間を確保するためのシステムを整備するなど、適切な労務管理を行うことが求められます。
02長時間労働に認定される恐れがある
もし430休憩のルールに基づいた休憩時間が確保できず、長時間労働と認定された結果、運転手を雇用している企業が処罰を受ける恐れがあります。
2019年から施行された「働き方改革関連法」では、上限を超える残業を強制した事業者に対して、ペナルティが科されるようになりました。
2024年1月以降「自動⾞運転の業務」の時間外労働の上限は年間960時間までと定められました。 この上限を超えた労働が確認された場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。(参考:働き方改革関連法解説)
企業は労働時間を管理し休憩時間を確保することは、運転者の健康と安全を守るだけでなく、罰則の回避にもつながることを意識することが大切です。
03残業代としての請求が発生する
企業が労働者の休憩時間を適切に管理できていない場合、残業代として請求が発生する可能性があります。
例えば、運転を中断している時間が荷待ち時間などに充てられた場合、それが「明確な休憩」とはみなされず、労働時間と判断されることがあります。
労働者が信用できる証拠を集め、実態として休憩がとれていなかったと認定された場合、企業はその休憩時間に相当する残業代を支払う義務を負います。
なお、賃金形態が歩合制の場合や、みなし残業時間制度を導入している場合も、企業に対して残業代を請求することも可能です。
未払いの残業代の請求は労使トラブルの原因となり、企業にとっても大きな負担になる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、企業は休憩時間の管理を徹底しましょう。
430休憩を守るための2つのポイント

運転者に430休憩の規定に基づいた休憩時間を取得してもらうために、頭を悩ませている企業の担当者の方もいるのではないでしょうか?
どれほどルールの遵守を呼びかけても、休憩時間の取り方はドライバーの判断に委ねられています。そのため、企業が運転者の休憩時間を正確に把握、管理することは難しい側面もありますよね。
430休憩を守るために備えておきたいポイントは2つあります。
それでは、順にチェックしていきましょう!
01安全に運転できる運行計画にする
運転者が安全な運転を行うためには、無理のない運行計画の作成が欠かせません。
適切な運行計画を用意することで、長距離運転による過労を防ぐだけでなく、業務を効率的に進める事にもつながります。
特に4時間を超える長距離運転を行う場合は、時期や時間帯による交通状況や休憩場所、荷物の積み下しのタイミングの見極めが肝心です。 あらかじめ迂回ルートや休憩場所の案をいくつか計画しておくことで、運転者の負担を大きく軽減することができます。
430休憩のルールをもとに、余裕を持ったスケジュールを組み立て、想定外のトラブルにも柔軟に対応できるような運行計画を作成しましょう。
02明確なマニュアルを作成する
企業は改善基準告示等をもとにしたマニュアルを作成し、ドライバーが遵守するべきルールを周知することが非常に大切です!
マニュアルには、
- 運転時間と休憩時間のルール
- 緊急時の対応手順
- 拘束時間に関するガイドライン
などの必要事項を明確に記載しましょう。
作成したマニュアルは従業員と共有するだけでなく、定期的な内容の見直しや研修により内容を深めることが重要です。 これにより、運転者の安全運転に対する意識を高め、企業としてコンプライアンス体制を強化することができます。

まとめ
ここまで、430休憩について詳しく解説してきました。
簡単におさらいしておくと「430休憩」は主な業務として自動車の運転を行う労働者が対象となる規定です。 連続運転時間は4時間以内に収めなければならず、4時間以内、または4時間を超えた直後に、30分以上の休憩を取ることが定められています。
430休憩の規定を遵守するためには、企業は効率的で無理のない運行計画を立て、適切な労務管理を行うことが求められます。ただし、企業側の努力だけでは休憩時間等の正確な把握は難しいという側面もあります。
そのためにも、このルールを運転者一人ひとりが正しく理解し、意識して業務に取り組むよう心がけることも非常に大切です。
株式会社コモンコムが展開している「LOGI-Cube」は、物流業務を効率化し、経営の「見える化」をサポートするシステムです。
運送管理の「LOGI-Cube EXPRESS」、倉庫管理の「LOGI-Cube STORAGE」、輸出入管理の「LOGI-Cube PORT」といった各分野に特化したモジュールで、幅広い業務に対応可能です。
詳しくはLOGI-Cube by COMMONCOMをチェック!
LOGI-Cube STORAGE(ロジキューブストレージ)